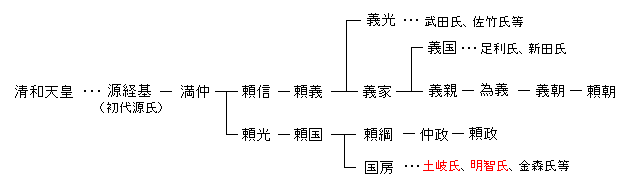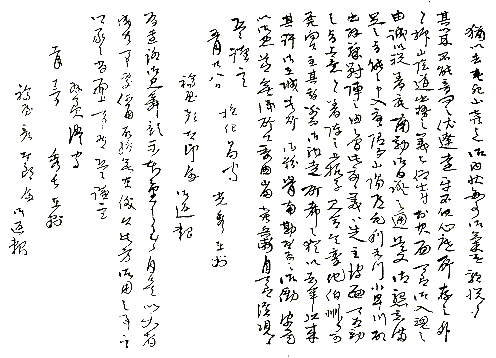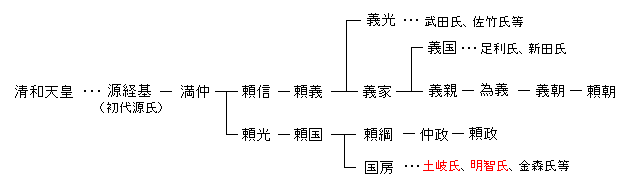
平氏と違って源氏には多くの系統があるが、史上最も有名なのは清和天皇の子孫で、六孫王と呼ばれた経基が源氏の姓を下賜されたのがそのはじまりである。
経基の子が満仲。
多田荘(現
兵庫県川西市多田)に住み、多田満仲と称した。その長男を頼光、三男を頼信という。
頼信の子孫には、後に日本史を彩る多くの武将が次々に現れている。史上名高い源氏の武将達、源義家、頼朝・義経をはじめ、足利氏、新田氏、武田氏などは、いずれも頼信の子孫である。今川氏、吉良氏、細川氏、山名氏など傍系を含めれば、膨大な数になる。
一方頼光の子孫は、坂東のように争いごとが多い地域にいなかったせいか、武名の高い人は少ない。
土岐氏はその頼光の子孫で、明智氏は土岐氏の支流になる。
光秀は1526年、あるいは1528年。美濃国の明智城(岐阜県可児市明智)で、明智光綱の子として生まれたとされている。
若いころは斉藤道三に仕えたが、1556年道三が嫡子義龍と争った時、義龍に明智城を攻められ城は落ち一族は離散してしまった。やむなく光秀は一旦は母親の実家を頼って若狭国に行き、後に越前で朝倉義景に仕官した。
足利義昭は将軍になる前、一時期、朝倉家に身を寄せたことがあった。
先代将軍の義輝が松永久秀に暗殺された時(1565年)、僧侶として興福寺一乗院にいた義昭にも危機が迫ったが、細川藤孝等の助けで寺を脱出し、各地を転々としながら越前国にたどり着いたのである。朝倉家を選んだのは身を保護してもらうためと、バックアップを得て将軍になるためであった。
義昭が越前に来て間もなくのことだろう。
光秀が細川藤孝と知り合ったのは。
後に両家は親戚となる。光秀の娘、珠(たま)は藤孝の子、忠興の妻になったから。有名な細川ガラシャだ。
もっとも一般的にガラシャと洗礼名で呼ばれるようになったのは、明治になってキリスト教が公認されて以降のことである。
それは余談。
朝倉義景にバックアップを断わられた義昭は、次に織田信長を頼ることを考えるようになる。
いつのことかはわからないが、光秀は朝倉家に仕官したものの、その前途に見切りをつけて義昭の家臣になっていた。義昭の使者として岐阜に行ったのが光秀だった。
一説によれば、斉藤道三の妻は光秀の叔母なので、道三の娘で信長の妻になった帰蝶(一般的には濃姫と呼ばれる)とは従兄妹同士だったという。それが本当なら、その縁で光秀が使者になったのかもしれない。1568年(永禄11年)7月のことだ。
信長は、足利義昭を岐阜に迎えるという、絶好のチャンスを見逃すような男ではない。彼が義昭を奉じて上洛の兵を起こしたのは、義昭を迎えたわずか2ヵ月後、9月のことである。その行動力は人間ばなれしている。
当時の光秀は、足利義昭に仕えると同時に信長にも仕えるというめずらしい立場で、今の言葉でわかりやすく言えば出向社員と言うところか。ともかくその後の光秀は、木下藤吉郎と共に織田家における最も有能な武将として出世街道を邁進することになる。その出世ぶりについては、重臣の柴田勝家が同僚(誰かは不明)に
近頃、あの表裏者の光秀がやたらと出頭(出世)しているが、わしは親の代から織田家に仕え、信長公からたびたびお褒めの言葉をもらっているので、うらやましがる必要など全然ない
と心中の不満を打ち明けていたほどだった。
あいまいな記憶だが、この話の出どころは確か武功夜話だったと思う。
この武功夜話というのは、実は史料としての信憑性には乏しく、柴田が実際にこんな話をしたのかはわからない。しかし、作り話だとしてもこんな話が作られるほど、光秀は実力抜群で信長の信任篤く、その期待に充分に応えていたのだろう。
光秀がいかに信長に重用されていたのかは、1571年比叡山焼き討ちの後、近江の滋賀郡を与えられ、坂本に築城し城主となったことでもわかる。この時点では木下藤吉郎さえ、自分の領地を貰ってはいない。
領地だけではない。
信長に仕えてわずかな期間で、柴田勝家や丹羽長秀といった普代の重臣に次ぐ位置にのぼったのである。
光秀はこうした待遇を、「自分は石ころ同然の身から信長様にお引き立ていただき、過分の御恩をいただいた。我が一族家臣は子孫に至るまで織田家への御奉公を忘れてはならない」と語ったと言う。
そんな光秀が、なぜ信長を討ったのか。
本能寺の変は戦国時代最大のナゾなのだ。
現在に至るまで、本能寺の変の理由は解明されておらず、いろいろな説があるが大きく分類すれば次のようになろうか。
| 1.怨恨 |
ドラマや小説でよく採り上げられるのがこれだ。
| (1) |
家康の接待役を命ぜられた光秀が悪臭のする魚を出したため、信長に罵倒され面目を失った |
| (2) |
領地を召し上げられ、まだ敵地の出雲国・伯耆国もしくは石見国に国替えを命ぜられた |
| (3) |
光秀が、稲葉一鉄の家来だった斉藤利三を召抱えたので、不満を持った一鉄が信長に訴えた。
信長が利三を一鉄の元へ返すよう命じると、光秀が拒否したため信長は光秀を突き飛ばした |
| (4) |
武田氏を滅ぼしたときの宴席で、光秀が「我らも骨を折ったかいがあった」と言ったのを信長が聞き咎め、「おまえごときが、いつ骨を折った」と面罵された |
| (5) |
どうしても八上城(敵城)が落せないので、母を人質に渡し開城させたが、信長の違約で母を殺されてしまった |
まだ他にもあるかもしれないが、きりがないのでこれくらいで止めておくが、ハッキリ言って、これらはただの俗説である。小説やドラマを作る都合上、光秀謀反の理由がわからなくては物語にならないのでこういう俗説が使われているにすぎない。
余談だが、史実と勘違いされている俗説の代表は忠臣蔵だろう。
おなじみの「刃傷松の廊下」。
浅野内匠頭がなぜ吉良上野介に斬りつけたのか、実は原因不明なのである。
吉良は浅野の相談役であり、浅野に不手際があれば責任を問われる立場だった。そんな吉良が、意味なく浅野を侮辱したり、失敗するように仕向けるはずがないではないか。
吉良は理由もなく、突然浅野に斬りつけられたのだ。
浅野の母方の縁者に法事の席で突然左右の人に斬りかかった人がいるらしいが、そのDNAが浅野にもあったのかもしれない。
吉良は翌年、赤穂浪士に惨殺されているし、現代に至るまで国民的悪役になっている。
忠臣蔵の最大の被害者は、吉良上野介自身だろう。
|
| 2.四国征伐 |
土佐の長宗我部元親は織田家とは友好関係にあって、光秀の家臣、斎藤利三の娘を妻にしていた。
しかし信長の方針が変わり、信長の三男、信孝を総大将として四国に攻め入ることが決定。このままでは娘の命が危ないと考えた斉藤利三が主人の光秀を説得したという説。(本能寺の変の翌日が織田信孝の出陣予定日だった)
|
| 3.焦慮 |
織田家の人事はすさまじく、能力を認められれば大いに優遇される反面、佐久間信盛のように信長の意にそわぬ者には容赦がなかった。光秀自身、いくつかの要因があって信長の信任が揺らいだと思うようになったという説。
| (1) |
光秀がかつて足利義昭の家臣であったため、義昭追放後には光秀に対する信長の心証が悪化したという |
| (2) |
羽柴秀吉の中国征伐の援軍が光秀であり、光秀が秀吉の格下になるのを嫌ったという |
|
| 4.野望 |
光秀も一戦国武将であり、天下を望んだため、信長を討ったという説
|
| 5.黒幕 |
本能寺の変は光秀の単独ではなく、背後に黒幕がいたという説
黒幕とは、
| (1)足利義昭 |
信長に追放された足利義昭が、かつての家臣だった光秀に命じたという説
|
| (2)朝廷 |
信長に滅ぼされるか、簒奪されるか不安になった正親町天皇、誠仁親王等が光秀に命じたという説。
その前提となるのは「三職推任問題」である。
信長が、朝廷側の打診(関白、太政大臣、征夷大将軍のいずれかに就任すること)に明確に回答しなかったのが、朝廷側の不安をさらに煽ったという説
|
|
以上、代表的なものをいくつかあげたが、日本史上あまりにも劇的な事件だったので俗説、憶測。諸説入り乱れるばかりで決定的なものはない。
明らかなのは、本能寺の変は計画的犯行ではない、と言うことである。
謀反を決意したのは信長が本能寺に宿泊するという情報を得たからであり、その後光秀は親しい友人で娘の舅でもある細川藤孝(幽斎)の援助を得ようと焦燥感に満ちた手紙を何通も送っている。その内容は天皇に政権を返すためとか、娘婿の細川忠興を取り立てるためとか、一貫性に欠けることはなはだしい。
光秀の謀反はただの思いつきであった。
じっくり時間をかけて計画してきたことではない。
信長を殺すことが唯一の目的であって、それ以外には何もなかったとしか言いようがない。
では、なぜ? と言うことになるが、一番関係しているのは光秀自身の性格だろう。
光秀にはこんなエピソードがある。
| 1. |
戦死した家臣の遺族には見舞の書状を送り、寺には供養のために金銭を寄進していた |
| 2. |
光秀の領内で年貢をごまかす農民がいたので家臣が罰しようとしたら、光秀は、仏のウソは方便と言い、武士のウソは武略と言う。それに比べれば百姓のウソなどかわいいものだ、と言ってそのままにしておいた |
| 3. |
民政が巧みで領民を慰撫していたため、今なお彼の遺徳を偲ぶ土地もある |
光秀は、心優しく家来思い、領民思いの殿様だったようだ。
私は謹厳実直、礼儀正しく、マジメで小心。物静かというよりは、いささか陰気なイメージを持っている。
天性明るく陽気な秀吉と違って、そんな光秀だからこそ信長のような破天荒な主君に仕えて、大変なストレスを抱えていたことは容易に想像できる。精神面のストレスだけに、休息しても癒されることはないし、その思いを打ち明ける相手もいない。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
以下は私の思いつきである。
足利義昭を迎えた時点での信長は美濃と尾張の大名であり、三河の徳川家康や近江の浅井長政と同盟してはいるものの、軍事的実力はそれほどのものではなかった。義昭の元から織田家に出向してきた光秀にはそれが心配であったろう。
しかしその心配は杞憂に終わった。
義昭を奉じた信長軍は、観音寺城の六角承禎(義賢)をはじめとする敵対勢力を圧倒的強さで蹴散らし、上洛に成功。
その後、京都で信長が見せた自軍兵士への統率のすさまじさは空前絶後といっていい。
なにしろ京都市民から、たとえ一銭でも盗めば死罪なのだ。
また将軍御所建設工事現場で、通りかかった女性をからかった織田軍兵士が、それを見ていた信長に一瞬のうちに首をはねられたのは有名な事件である。
信長は、何も京都市民に迎合するために、こんなことをしたのではない。
それが信長の性格なのである。
信長は、元不良少年だっただけに、自分は好き勝手なことをしていたが、他の人間には絶対の忠誠と規律を求める男だった。
その規律もこのようにハンパではない。
天下を治めるにはこれくらいの秩序感覚がなくてはならないだろう。
そんな信長に接して、この男なら大丈夫・・・
光秀はそう確信したに違いない。
しかし次第に光秀は、信長に不安を感じるようになる。
最初は信長が副将軍就任を断ったことだった。
なぜ信長は副将軍を受けなかったのか、光秀には信長の「計画」がわからない。
さらには信長が使用した「天下布武」の印。
天下布武とは武力で天下を治めるということではないか。その資格を持っているのは将軍以外にいないはずだ。
副将軍を断わったうえに天下布武とは、信長は何を考えているのか。
その不安は、わずかな期間で現実のものになった。信長の義昭追放である。
光秀は義昭の家臣でもあったが、この時点では完全に信長の家臣になっていた。仮に義昭の家臣だったとしても譜代ではないし、共に没落するのは真っ平と考えたのだろう。この点、彼もまた、戦国人ではある。
次は、本願寺や比叡山との徹底した戦闘だった。
光秀は当然仏教信者であり、反キリスト教である。
当時の比叡山が純然たる宗教団体ではなく、修行を怠り、戒律を破り、女を引き入れ、俗人さえ顔を赤らめる行為の数々重ねていたことは誰でも知っていることだった。それでも長い歴史と伝統を持つ比叡山の攻撃は、光秀に相当の衝撃を与えたのではないか。各地で行われた一向宗徒の殲滅作戦もまた。
その衝撃は信長の将来に対する不安になってくる。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
やがて光秀は、これ以上の衝撃はないほどの衝撃を受ける。
信長の「作品」、つまり安土城を見たのである。
安土城は信長の理想を具現化したものだが、それを理解するには相当な教養を必要とする。
普通の武士にはわからない。
なにしろ当時の武士は戦いに強ければ、無学でも文盲でも、恥でもなんでもなかった時代だったのだ。秀吉はいうに及ばず、信長も柴田勝家以下の家臣達も、せいぜい手紙が読み書きできる程度の教養しか持っていない。
ところが光秀は、当時の武士にはめずらしいほどの教養人で、中国の古典をはじめ諸学に通じ、詩作や和歌を詠むこともできた。
(戦国後期最大の文武両道の名将と言えば伊達政宗だと思うが、この人は例外中の例外であろう。)
地下の宝塔、吹き抜け、五階や六階に描かれた華麗すぎる絵画。最上階に描かれた天人影向図・・・おそらく安土城天主の内部を見た家臣の中で、光秀は真っ先に信長の真意を理解したのではないか。
それぞれの絵の意味、描かれた意味を考えていった光秀は、天皇にとって恐るべき信長の考えを読み取ったのではないか。もっとも光秀という人は、信長や秀吉と違って頭の回転が速い男ではないから、それなりに時間はかかったとは思うが。
次に理解したのは秀吉だったのではないか。
秀吉は元々があの生まれである。三皇五帝や太公望、孔子、老子等、古典の知識などあろうはずがない。
最初は天主内外の華麗さに驚き、次になぜ信長はこんな絵を描かせたのか不思議に思ったことだろう。そして織田家中一の教養人だった光秀に、いろいろ質問したことだろう。
しかし光秀は、信長の真意がわっかても、それをたとえ同僚の秀吉にも言うわけにはいかない。
コトはあまりにも重大すぎる。せいぜい、描かれた人物の業績を語ったぐらいだったろう。
秀吉の頭の回転の速さは、光秀などの比ではない。
光秀の説明で、たちどころに信長の「真意」を覚ったに違いない。
当然、胸に秘めて口外はしない。
秀吉は神として地上に君臨するという考えを、信長に教えてもらったのだろう。
しかしさすがの秀吉も生前に神になるのは無理で、死後神になった。豊国大明神という神に。
秀吉は信長の思想を積極的に理解しようとし、その思想の賛成者側に回ったことだろう。
そうでもしなければ、生きていけない秀吉であったから。
しかし光秀は違った。
光秀の驚きは、信長への恐怖に変わる。
唐土(中国)とは違い、わが国では主従の区別は厳然としている。それは誰にも変えられないはずではないか。(これを書きながら、私は古代に起きた道鏡の事件を連想している。)
光秀は王者と覇者の違いを知っていた。
王者とは天子が徳を以って天下を治めるもの、覇者は武力や権謀で治めるもの。
信長に、いったい何の徳があるというのか。
朝廷を信長から守らねばならない。
勤皇家の光秀は、次第にそう思うようになったろう。
もちろん朝廷側は、そんなことは知らない。
朝廷を守るには、信長を殺さなくてはならない。
しかし自分にそんな大それたことができるのか。
マジメで小心だっただけに、それ以降の光秀は、ほとんどノイローゼ゙状態だったのではないか。
それでなくとも野戦攻城の日々は、いやがおうにも光秀にストレスを与えていく。
信長の家臣追放事件が追い討ちをかける。
織田家に林秀貞という家臣がいた。
かつては林通勝と伝えられてきたが、通勝は間違いで秀貞が正しいらしい。
1552年、信長は父・信秀の死後家を継いだが、決して順調に家督を相続できたわけではない。
なにしろ「たわけ殿」である。反対派がかなりいた。
信長に勘十郎信行という弟がいた。
「たわけ」の兄と違って、利発で折り目正しい若者だったらしい。
信行は後に信長に暗殺される(1557年 享年21歳)。
その信行を織田家の当主に、とバックアップしたのが林秀貞と柴田勝家だった。
時には戦闘もあったが、信行の死後は2人とも許されて、家中での地位も変わりなくそのまま信長に仕えてきた。柴田は織田軍団の先鋒将軍だったし、林は武将としては必ずしも有能ではなかったが、事務官として行政面や外交面ではそれなりに実績をあげていたようである。
しかし1580年。
信長は突然、30年近くも前の信行擁立の罪を書き並べ、林を追放してしまうのである。
こうなるとリストラと言うよりは、難癖としか言いようがない。
そのくせ林と同罪であるはずの柴田勝家には何の咎めもない。
理由はただ一つ。
信長にとって柴田は有能であり、林は無能だったと言うことだけである。
これだけではない。
信長と本願寺との戦いは10年の長きにわたったが、1576年、指揮官だった塙直政の戦死後、新たに任命されたのが佐久間信盛だった。この時点で佐久間は織田家最大の軍団を指揮することになる。
しかし佐久間の指揮官ぶりはいたって芳しくなく戦線は膠着し、1580年になって信長が天皇を動かしてようやく和睦にこぎつけたのだ。
同年8月、佐久間信盛は信長から19条からなる折檻状を突きつけられ、嫡男信栄と共に高野山に追放された。さらにその後、高野山にいるのも許されず、立ち退きを命ぜられたのだった。
譜代の家臣だった林秀貞と佐久間信盛の追放は、はかりしれない衝撃を他の家臣達に与えることになる。
いつかおれも林や佐久間のように、身一つで追放されるのか。
光秀でなくとも、織田家の重臣達は全員そう思ったことだろう。
これだけではない。
天下統一という目標のため、信長は自分自身を酷使したが、同様に家臣達にも休息を与えなかった。織田家の家臣達は、有能であればあるほど疲労の極地にあった。
では、どうすればいいのか。
簡単に結論が出る問題ではない。
1582年5月27日、中国行きを命ぜられた光秀は、出征前に愛宕山の威徳院を参拝した。
戦勝祈願であろう。
翌28日。光秀は威徳院で連歌の会を催した(愛宕百韻)。
出席者は里村紹巴(連歌師)、里村昌叱(紹巴の一派)、里村心前(同)、行祐(威徳院住職)、猪苗代兼如(連歌師)。
ここで光秀は発句として、後世に有名なあの句を読み上げるのである。
時は今雨が下しる五月哉
第二句は行祐。
水上まさる庭のまつ山
それを受けて里村紹巴が詠む。
花落つる池の流れをせきとめて
昔から「時は今雨が下しる五月哉」は、「土岐は今 天が下治る
五月哉」の意味で、土岐一族の光秀が天下を治めるという意味とされている。
「水上まさる庭のまつ山」は、水上とは源(水源)のことで庭は朝廷のこと。朝廷が源氏(光秀)を待っているという意味で、行祐は光秀の謀反を容認したとされている。
続く「花落つる池の流れをせきとめて」は、水(光秀)の流れ(謀反)を止めるという意味で、里村紹巴は謀反を止めさせようとしているとされている。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
しかし・・・この話は、あまりにもできすぎてはいないか?
これらの句は奉納されているので、光秀が、時は今・・と詠んだのは確かなことだ。
この句を土岐は今と解釈したのは、本能寺の変というその後の事実から後世の人がコジツケたのではないか。第二句以下もまた同じである。
なぜなら光秀はこの連歌の会の後、中国へ出征するという手紙を伯耆国の国人、福屋隆兼に書き送っているのだ。この書状は現存している。
内容を意訳すると次のようになる。(原文を見てもわからないので、「だれが信長を殺したのか /
桐野作人」より拝借しました。)
なお去年のことだったか、(家来の)山田喜平衛までご案内いただき、いつもお気遣いいただき歓悦しております。それ以来、便りができませんでした。遠く離れているので思うようにまかせず残念です。さて、(信長が)山陰道に出陣するように仰せになったことについて、その方面でご入魂になれたら、まことに喜ばしく思います。
南条元続が内々にお示しのとおり、これまたご懇意にされている様子、(私も)満足している旨よくよく(南条に)申し入れたいと思います。したがって、山陽道に毛利輝元、吉川元春・小早川隆景が出陣することになり、羽柴秀吉と対陣しているので、今度の儀(出陣)はまず、その方面(備中)でつとめるようにとの上意です。
(備中)に着陣のうえ、様子を見て(方向を)変え、伯耆国へ発向するつもりです。そのときは格別に馳走されるよう望んでいます・・・以下略。
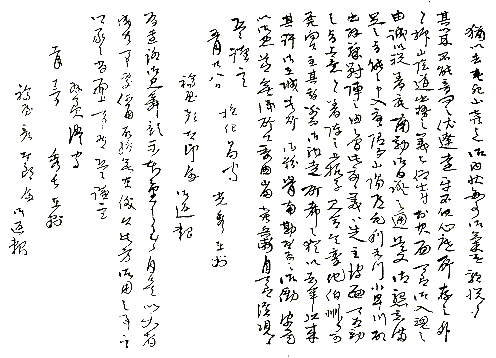 |
|
福屋隆兼に宛てた光秀の書状
(東京大学所蔵)
|
この手紙について、桐野作人氏はこう述べている。
光秀がこの書状を書いた目的・思惑については、すでに謀反を決意していたから、なにより秘図をカムフラージュする必要があったという見方がまず想起されそうだ。
しかしそうした見方に対しては、伯耆という遠国の国人にカムフラージュしてまでいかなる効果や役割を期待するのかという反論がただちに可能である。
さほど急用とも思えない内容だから、カムフラージュする手間をかけるくらいなら、書状を書かなければよい。書かないほうがましなのにもかかわらず、あえて書いたのは、光秀が中国に出陣するつもりでいたからだと考えるしかない。だから、書状の内容はカムフラージュでもなんでもなく、少なくともこの日の光秀の心情を率直に表現しているとみるべきだろう。
つまり、光秀は謀反のわずか三日前でも、まだ謀反を最終的に決断していなかったのである。たとえ叛意を抱いていたとしても、挙兵をいつ、どこで、どのようなかたちにするのか、まだ具体的に考えていなかったのではないだろうか。
(だれが信長を殺したのか / 桐野作人)
愛宕百韻の時点(5月28日)で光秀は、叛意はあったとは思うがまだ決断していなかったのだ。
だから私は、「時は今・・」の句は後になってのコジツケではないかと思うのだ。
そして翌29日。
光秀は、信長がわずかな供回りを引きつれて、本能寺に宿泊することを知った。
朝廷と信長との間で悩み、心身共に疲労の極致にあった光秀は、ここでついに決断した。
いや、決断というよりは発作であったろう。
信長を討った後のことなど考えてはいないし、そんな時間もなかった。
光秀の心中を打ち明けられた斉藤利三以下の明智家重臣達は、なぜ諫止しなかったのか。冷静にならずとも、少し考えればそんな思いつきの反乱など成功するはずがないと、誰もが思ったことだろう。
前記したように光秀は、家来思いの殿様だった。
その恩に報いるため、重臣達は光秀の話を聞いて仰天すると同時に、すぐに死を覚悟したのではないか。常に死と隣り合わせに生きてきた彼等戦国人の覚悟の良さ、思い切りの早さは現代人の想像をはるかに超えているのだ。
ちなみに明智家の筆頭家老の斉藤利三は乱の後、捕らえられて処刑された。
その娘が春日局である。
かくして信長のプラン、「神への道」は彼自身、思いもかけないことで挫折してしまった。
その後の詳細を書いてもしかたがない。6月13日、山崎の合戦に敗れた光秀は坂本に落ちる途中、小栗栖で死ぬ。
光秀の辞世
| 順逆無二門 |
(順逆二門に無し) |
| 大道徹心源 |
(大道心源に徹す) |
| 五十五年夢 |
(五十五年の夢) |
| 覚来帰一元 |
(覚め来れば 一元に帰す) |
私にはこの意味がわからない。
自信はないが、あえて書けばこのようになろうか。
私にとって、順う(したがう)とは天皇に対してであって、主君(信長)への反逆は矛盾したことではない
そのことは、もとより心に命じていたことである
天皇の役に立たんと願った我が55年の夢は
今ここに覚めて、私は旅立たんとす
参考資料(順不同)
日本史(ルイス・フロイス)、室町時代の王権(今谷明)、戦国時代と天皇(今谷明)、天皇家はなぜ続いたか(今谷明)、信長と天皇(今谷明)、集中講義
織田信長(小和田哲男)、信長公記、信長と十字架(立花京子)、足利義満
消された日本国王(小島毅)、復元・安土城(内藤昌)、だれが信長を殺したのか(桐野作人)