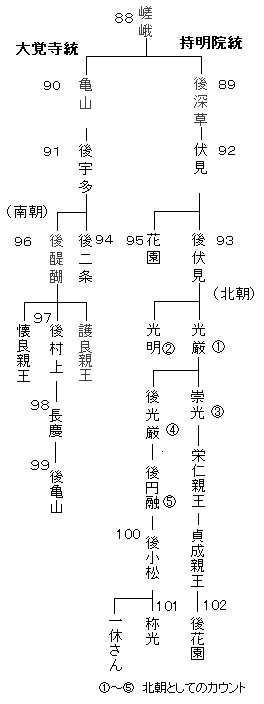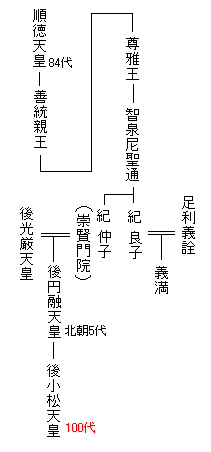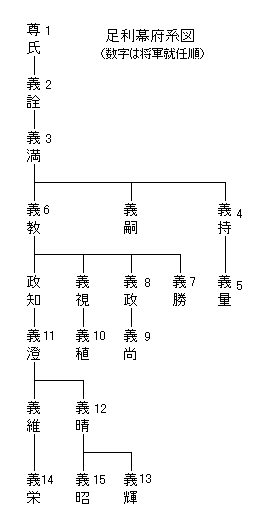Index
ティータイム 前へ 次へ
信長、神への道 4
■室町時代の天皇
室町時代初期から戦国時代にかけて、天皇とはどんな存在で立場だったのか。話は脇道に入るが、信長の朝廷政策を書く前に簡単に記しておく。
鎌倉時代、承久の変(1221年)以降、軍事、裁判、外交、政治など、多く権限が武家に移行してしまったが、天皇(上皇)にとって残る権限は改元、皇位継承、叙任、祭祀などで、権威はかなり低下してしまっていた。
これが室町時代になると、朝廷の権威はさらに失墜してしまう。理由は日本を真っ二つに割った南北朝の動乱(1336〜1392)である。
南北朝の原因は歴史の流れを無視した後醍醐天皇の妄想にあったが、足利尊氏も対抗上別の天皇を立てざるを得ない。これが北朝である。
1351年、愚劣な事件が起こり、天皇の権威は更に低下する。
足利尊氏と弟の直義との争いである(観応の擾乱)。
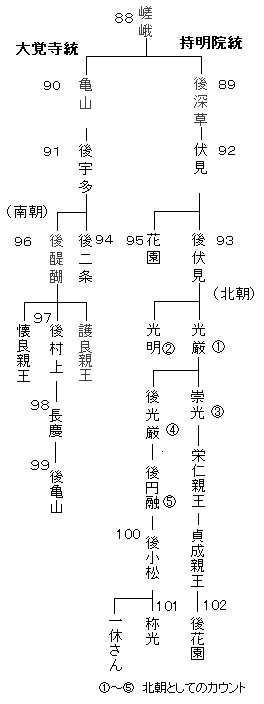 |
この時、尊氏は一時的に南朝に降伏。南朝側は京都へ進攻して尊氏の嫡男足利義詮を追い、京都を占拠することになる。
その後、義詮は京都を奪還するが、南朝側は撤退する際に、三種の神器と共に光厳・光明両上皇、崇光天皇と直仁親王(崇光の皇太子)を、賀名生(奈良県)へ連れ去った。これで京都には上皇と天皇が不在になってしまった。(この時点で上皇、天皇は退位)
南朝側の天皇親政に対し、北朝側の政治システムは院政である。平安中期から朝廷の実権は天皇から上皇へ移り、実権は上皇が握ることになっていた。
しかし上皇なら誰でも実権を握れるわけではない。
この時代は現代と違って天皇は生前に退位することが多く、元天皇は複数いる場合があった。その父親も生きていれば上皇なので、上皇も複数いることがある。
複数の上皇のなかでも実権を握れるのは一人だけで、別名、治天の君(ちてんのきみ)と呼ばれ、公家(摂政)、神社(護持)、武家(守護)の各勢力の上に立つ存在だった。これに反して天皇にはほとんど実権はなく、上皇や治天になるための研修期間と言っていい。
さて一時的ではあったが、京都は治天も上皇も天皇もいない状況になった。
そこで僧侶だった光厳上皇の皇子、弥仁親王(いやひとしんのう)が拉致されず京都に残っていたため、急遽天皇に推戴することが決まった。
ところが治天がいなくては新天皇の任命ができないし、朝廷内の他の政務や儀式が停滞することになる。
困り果てた幕府は、光厳上皇の母親、西園寺寧子(広義門院
1292〜1357)に治天の君になってくれるよう頼みこむのである。
西園寺寧子、60歳。
当時の感覚でいえば相当の高齢である。当然はじめは断わった。
彼女は、なすすべもなく上皇・天皇と直仁親王が拉致されたのは幕府と公家の無能によるものと、彼等への不信をアラワにしていたのだ。
しかし結局は説得に負け、彼女は女性として日本史上唯一の上皇、治天の君になるのである。
|
しかし三種の神器がない。
やむかく幕府は窮余の策として、神器が入っていたカラ箱を神器に見立てて弥仁を新天皇にした。北朝4代、後光厳天皇(1338〜1374)である。神器なしの即位は、すなわち天皇の権威の失墜でもあった。
そして三代将軍足利義満(1358〜1408)の時。天皇家は存亡の危機に直面する。
義満による天皇家簒奪計画である。
◆足利義満の野望
天皇家を簒奪する・・・そんなことを足利義満自身が他人に語ったわけではないし、当時の史料に載っているわけでもない。
今に残る様々な史料を状況証拠とした推論である。
だから天皇家簒奪計画を唱える学者もいれば、同様にこれを否定する学者も多い(私は前者です)。
1367年、二代将軍義詮の後を継いだ義満は、わずか11歳の少年だった。
少年将軍の代理として、1379年に失脚するまで実際の政治を行ったのは、管領の細川頼之(1329〜1392)だったが、その詳細は書く必要がないので省く。
同様に義満の業績で一番知られているのは、1392年の南北両朝統合だと思うが、その経緯もここでは書かない。簡単に言えば統合は義満が南朝を騙した結果だった。
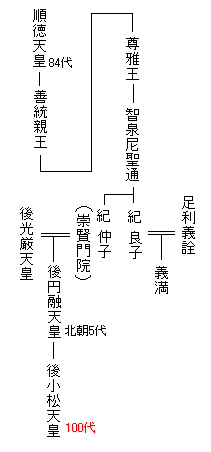 |
1361年、義満が8歳の時。
京都は南朝方の楠木正儀(正成の子)に京都を占領され、義満は赤松則祐の居城播磨国白旗城に避難したことがあった。
翌年には北朝方が京都を奪還したため帰京したが、岐路、摂津の国に泊まった際に周辺の景色が気に入り、「京都に持って帰りたい。お前らが担げ」と家臣達に命じたので、家臣達は義満の気宇壮大さに驚いたと言う。
本当にあった話かどうかはわからないが、わずか8歳でこんなことを言う子もめずらしいと言うべきか、子供のころから大器の片鱗を見せていたと言うべきか。
さて何が契機となって義満が天皇家簒奪計画を考えるようになったのかはわからない。彼の計画は、二男の義嗣を天皇の養子にして皇位を継がせ、自らは上皇(治天)として君臨することだった。
治天になるための血筋に不足はない・・義満はそう思ったことだろう。
足利氏は、疑いもなく清和天皇を祖とする源氏の一族だが、それだけではタダの末裔ということで、そんなのは他には武田氏、今川氏、山名氏などいくらでもいる。
しかし母方の系譜をさかのぼれば、義満は84代順徳天皇の五世の孫なのである(左の系図)。
かつて26代継体天皇(450?〜531)は、応神天皇(10代)の五世の孫だった。おそらく義満はこのことを知っていただろう。おまけに現天皇の後円融は、自分のイトコではないか。
|
さらに当時、朝鮮に王家を簒奪した格好のサンプルが存在したのだ。
その男は李氏朝鮮の創始者、李成桂(1335〜1408)という。
◆明の建国
14世紀半ば、元の支配下にあった中国大陸では、大規模な農民の反乱が起きていた(紅巾の乱)。
現在の安徽省で貧農の子として生まれた朱元璋(1368〜1398)は、この乱に身を投じて頭角を現し、ついには元朝を倒してあたらに明を建て初代皇帝になった。洪武帝である。
朱元璋の皇太子は長男の朱標だったが、早死したので朱標の子が二代皇帝として即位した。つまり朱元璋の孫である(建文帝)。しかしこれを不服とした朱元璋の四男朱棣は、クーデターを起こして建文帝を廃し、自分が皇帝に即位するである(永楽帝)。
つまり一族間の争いとはいえ、明の三代皇帝は一種の簒奪者と言っていい。
一方朝鮮半島では、高麗王朝の武将に李成桂という男がいた。主家の内紛に乗じて実権を握り、1392年、王族の一人だった王揺(恭譲王)を王位につけたが、後にこれを殺害し自ら王朝を築いた。これが20世紀まで続く李氏朝鮮である。
中国でも朝鮮でも簒奪者が王位についている。オレもやってやれぬことはあるまい・・義満はそう考えたであろう。
(王族、王揺、王位と王が連続してわかりにくい。王族とはKing
の一族。王揺の王はKingではなく、姓です)
この時期、後醍醐天皇の二男、懐良親王(かねよし 1329〜1383)は征西大将軍を称し、九州にあって着々と南朝方の勢力を拡大していたが、この懐良が明に朝貢し、臣従したのである。
その結果、懐良は明から「日本国王」として認知されることになった。
私のホームページで他のコンテンツにも書いてはいるが、朝貢とか国王というのは少々説明を要する。
古来東アジアの政治的秩序は、中国皇帝を頂点とするいわゆる冊封体制であった。
この体制を簡単に説明すると、かつて(今でもその傾向はあるけど)中国は自らを中央の華と称し、周辺諸国を東夷、西戎、北夷、南蛮と呼び野蛮国扱いしてきた。日本は東夷になる。そのことを書いた古文書が、魏志倭人伝の中の「東夷伝」である。
さらに中国皇帝は、周辺諸国と対等の国交を一切認めない。
日本や朝鮮、安南(ベトナム)など周辺の「野蛮国」の首長は、中国と国交を結びたければ貢物を持って中国皇帝に使者を送り、臣従を誓うのである(朝貢)。
中国と国交を結ぶとは、裏を返せば中国に攻め滅ぼされたくなかったら、という意味になる。いいの悪いのと言ってもはじまらない。かつて中国はアジア最大の(世界最大と言うべきか)軍事大国だったのだから。
朝貢の見返りとして中国皇帝は、その首長に王の称号を与える。古代、卑弥呼が魏から「親魏倭王」の称号を得ているのはその結果である。また受け取る方が驚くほどの「おみやげ」も貰う。
そりゃそうでしょう。
中国の沽券にかけても、野蛮人から貢物を貰いっぱなしにするわけにはいかないのです。ですからおみやげは、貰った貢物の数倍の価値ある物品になります。一例をあげれば三角縁神獣鏡です。また朝貢のお返しとして、中国皇帝は「臣下」である各地の王を保護する義務があった。後年、豊臣秀吉の朝鮮侵略の時、明が朝鮮に援軍を送ったのはこの理由からである。
明に朝貢し日本国王の称号を下賜されるのは懐良にとって屈辱だったかもしれないが、父親の後醍醐天皇が徹底した朱子学カブレだったから、それほどでもなかったかもしれない。懐良にしてみれば、明のバックアップを得て北朝(足利幕府)に対抗するつもりだったのだろうが、足利義満にすれば、いや、日本にとっても明の援軍が来たら一大事であった。しかし幸いなことに、明は日本に軍隊を送り込まなかった。
懐良が明に援軍を依頼したかどうかはわからない。もし依頼して明軍と南朝の連合軍と戦ったら、おそらく北朝は滅びただろう。そうなれば明軍が日本に残って、南朝を傀儡政権として日本を支配したかもしれない。
ところで邪馬台国などはいざ知らず、かなりの昔から日本は中国と対等のつもりだった。
それは天皇という日本の帝王の称号にも表れている。
日本の帝が天皇を称すること自体、中国皇帝から見れば不敬なことであった。
皇という文字を使えるのは中国皇帝以外にはないのだから。日本の帝があえて天皇を称したのは冊封体制から脱却し、中国とは別の独自の道を歩むことのアピールだったが、中国から見れば夜郎自大。野蛮人が何言ってるか、というところだったろう。
こうした不敬はしばしば開戦の理由になるが、古代中国が日本を攻めなかったのは、やはり間に海があったことと、日本が相当の遠隔地だったからだろう。
懐良の勢力は長続きしなかった。
1372年、九州探題今川了俊に大宰府を追われた懐良は筑後に落ち、失意のうちに死ぬ。
◆日本国王義満
1381年、義満は内大臣に就任。翌1382年には左大臣、1383年には准三后の宣下も受けた。
准三后とは太皇太后、皇太后、皇后の三后に准ずると言うことで、后の字から女性に与えられる称号と思われるかもしれないが、実際には男女の区別はない。
准三后の宣下を受けるとは、臣下ではなく皇族の待遇を受けることを意味する。
最初に准三后となったのは、藤原良房(804〜872)である。
1383年には武家としてはじめて源氏長者になっている。
源氏を姓とするのは、源頼朝や足利尊氏等の清和天皇の子孫が最も有名だが、その流れだけではなく嵯峨天皇、村上天皇の子孫にも源氏を称する一族がいる。
源氏長者とは、特定の系列(天皇の子孫)の源氏だけではなく、すべての源氏のトップになるということであり、源氏のなかでの召集権、裁判権、官位の推挙権などを持つようになる。
当初、源氏長者は嵯峨天皇の系列から出ていたが、やがて村上天皇の系列から出るようになってからは、ずっとその出身者が長者とされてきた。後年、足利家からは義満以外では4人の長者を出したが、江戸時代になると徳川家が独占するようになった。
さて左大臣として准三后として源氏長者として、義満は名実ともに公武両勢力の頂点に上り詰めのだ。
しかし義満はコトを急がない。
本城を落すには外堀を埋め、三の丸、二の丸と、少しづつ本丸に近づかなくてはならない。
まず自分(義満)の権力にハクをつけなくてはならない。
義満が明に使者を送り、懐良親王につづいて日本国王の称号を得たのは1401年のことである。
しかしいきなり国王の称号が得られたわけではない。
1380年、義満は「日本国征夷将軍源義満」として、明に使者を送ったが相手にされなかった。
そもそも将軍とは、帝王の臣下にすぎない。
だから明にとって日本国征夷将軍というのは、明の皇帝の臣下である日本国王の、さらに臣下ということになる。臣下の臣下を陪臣(ばいしん)というが、皇帝は陪臣から書状を受け取ることはない。(このような形式主義は日本でも中国でも同じである)
1395年、征夷大将軍と太政大臣を辞任した義満は、同年得度し法体となり道有、次に道義(どうぎ)と名乗るようになった。官職を辞し、仏門に入ることは天皇の臣下であることを辞めたということだった。
この時、四辻季顕、中山親雅、徳大寺実時、今出川公直等の公家だけではなく、斯波義将、細川頼元、一色詮範といった幕府首脳も義満に続いて頭を丸めてしまう。
関白だった一条経嗣が、驚いて「このままでは公家がいなくなてしまう」とこぼすほどだった。
この出家ラッシュ現象は義満に追従するものとしても、義満自身の考えは次のようなものだったろう。
出家して道義と称し天山と号しても、それは世俗から絶縁するためではなく、むしろ世俗の束縛からぬきんでて自由な身となり、より強力に世俗を支配せんがためであった。
出家の身には公家も武家もなく、より高次の世界に住するものとして公武の世界に君臨したもので、義満はその先例を清盛もとめたのであろうとの説は尤もである(足利義満/臼井信義)
官職を辞し、出家することによって義満は天皇という束縛からわが身を解放し、自由人として天皇(治天)とは別の王権を築こうとしたに違いない。
王権とは、王が自分以外を支配するために持つあらゆる権利を指すが、この権利は奪うことができる。だから古今東西を問わず、王は自己の王権を守るため、様々な権威づけをおこなってきた。一例をあげればヨーロッパの王権神授説だろう。また天より人類の監督者に任命されたとする中国式権威も同類と言える。
こうした権威を簡単に言えば、「王権は神(天)より与えられたものだから、何人(なんぴと)たりともこれを犯すことはできない」という考えで牽強付会もはなはだしいが、元々王権というものは幻想なのだから、こじつけでもなんでもかまわないのだろう。
さて義満も、自分の王権(この段階では王権といえるかどうか・・??だが)を守るため、一定の権威づけをする必要があった。彼は、その権威を宗教のような目に見えないものではなく、明の臣下になること(日本国王になること)に求めたのである。
すなわち朝貢の再開であった。
1401年義満は、「日本国准三后道義(義満)、書を大明皇帝陛下にたてまつる」という書き出しではじまる国書を明に送った。翌1402年2月、明の建文帝は、「爾(なんじ)日本国王源道義、心を王室に存し、愛君の誠をいだき・・」と返書を発している。
同年9月、建文帝の返書を携えた明の使者団が来日。
京の北山第に到着した一行を、義満は自ら出迎え返書に三拝九拝した。
北山第では左大臣近衛良嗣と、内大臣今出川公行といった重臣も出迎えている。返書に三拝九拝した義満の臣下そのものの態度は、並み居る公家達の反感を買ったが、義満の機嫌を損ねることを恐れる彼等は何も言えなかった。ともあれ、ここに足利義満は、日本国王として明から「認知」されたのだ。

|
北山第(きたやまだい)とは義満にとっての「政庁」であり、
有名な鹿苑寺(金閣寺)はその一部に過ぎなかった
|
1382年、後円融天皇が譲位の意向を示した後、天皇候補は2人いた。
後円融の子の後小松と、従兄弟の栄仁(崇光天皇の子)である。
後を継いだのは、義満のバックアップを得た後小松だった。これで後小松天皇は、完全に義満の傀儡になる。
1394年、後円融が死ぬと、義満は周囲の反対を押し切り、「父に準ずる」と言って、強引に南朝側の後亀山を後小松の上皇としたのだ。これはあきらかに人事権の奪取だった。
天皇も上皇もオレの一存でどうにでもなる・・・義満はそう思ったことだろう。
1395年、太政大臣に任命され、任命式のため朝廷に出仕した義満を、関白一条経嗣が出迎え拝礼するという出来事が起きた。関白とは太政大臣より上位なのだが。
また宗教においては、自分の息子達を門跡として、天台座主・仁和寺門跡・青蓮院門跡・大覚寺門跡に送り込むことに成功した。門跡とは、皇族出身者が住職となる特定の寺院の最高権力者であり、そこに子弟を送り込むということは仏教界の権威を手に入れることになる。
加持祈祷といえば天皇が主催する国家行事だった。
言うまでもなく天皇(天皇家)個人のことから、国家安泰にいたる除災招福のオマジナイである。
出家して以来、義満は加持祈祷など宗教儀式に没頭するようになり、ついには宮中でのみ行なわれていた儀礼の場を北山第で執り行うようになった。天皇の重要な権限であった祭祀権の奪取といっていい。
もはや上皇、天皇、関白。
誰も義満の暴走を止められない。
◆義満の死
おそらく平安時代のころからだろう。
野馬臺詩(やばたいし)という不思議な予言詩(あのノストラダムスの予言のような)が、京の公家達にひろまっていた。内容は、どんな王朝であれ帝王は100代で滅び、代わって猿・犬に等しい卑しい血筋の者が帝王になるというものだった。
この帝王は100代で滅びるというのは百王説といって、これも古くからあったが野馬臺詩はこれをもとに作られたイタズラ者による創作である(と私は思っている)。
詳細はこれ以上は書かないが、これが当時信じられていたし、公家たちはそれに恐怖していたという事実は重要であろう。
義満がこれを利用したという史料はないが、時の後小松天皇がちょうど100代になるので、これは義満にとっては自己の王権を正当化するための宣伝の一つとして大いに利用したかもしれない。
後小松天皇の母親が危篤になった時、見舞に行った義満は居合せた公家達と協議して、後小松天皇は先年(1393年)父・後円融天皇の喪に服したばかりだ、それなのに今度は母の喪とは。
天皇一代で二度も父母の喪に服するのは凶であるから、形式上でもいいから准母をたてなければならないと強弁し、関白一条経嗣等を説得し、自分の妻の日野康子を後小松の准母にしてしまったのだ。
これは何を意味するのか。
形式上とはいえ自分の妻が天皇の母ということは、自分(義満)は准父(天皇の父)になったということだろう。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
さて義満の計画は大詰めを迎える。この段階では長男義持は4代将軍である。
1408年、出家させていた二男の義嗣を還俗させたが、これ以降、義嗣は尋常ではない昇進をする。
1408年3月4日、元服前(14歳!)では異例の従五位下になったのを皮切りに同年3月24日、正五位下左馬頭。同月28日、従四位下。翌29日、左近衛中将。翌月(4月)25日、元服し従三位参議という具合である。
この年の3月8日から28日まで後小松天皇は、義満に招かれて北山第に行幸した。義満、義嗣父子はそろって天皇を出迎えた。ここで天皇の座は繧繝縁(うんげんべり)の畳だったが、対面する義満の畳もやはり繧繝縁だったのである。
 |
|
繧繝縁の一例 |
繧繝縁の畳とは上皇、天皇、三皇后以外には使用が許されない畳の縁で、現在でも「繧繝縁は位階のある人のみが使用を許された柄ですので一般人は使用してはいけません」と紹介されているほどである。
北山第には当然ながら天皇だけでなく、関白以下廷臣達が大勢いた。義満は彼等に「見せつけた」のである。「異例」はさらに続いた。
8日の対面の座では、義嗣は、後小松から「天盃」を受け、笏(しゃく)を取って庭上で舞踏した。その間、関白以下諸卿、みな庭上で蹲踞(そんきょ)するという異様な礼式で、元服前の童子が天盃を受けたのが未曾有なら、童姿で笏をもったのも先例がなく、これすべて義嗣を将来の大役に仕立てようとする義満の演出であった。
(室町の王権/今谷明)
天盃とは、早い話が天皇の「お流れ」である。この盃は義嗣の次に関白が受けたという。関白は臣下の最高位。本来なら最初に受けるべき立場だった。
また、笏とは下の画像のように官人が正装したとき威儀を正すために持つ細長い板のこと。初めは朝廷の公事を行うときに、司会者が備忘のため式次第を紙に書いてこの裏に貼っていたらしい。
 |
|
これが笏 |
4月25日、義嗣の元服式は、内裏で親王の格式に准じて行われた。破格の儀礼であった。
義嗣が後小松の皇太子になる日は近い・・義満はそう確信しただろう。
しかし、最後の土壇場で天は義満に味方しなかった。
4月28日原因不明の病にかかった義満は5月6日、あっけなく死ぬ。
義満にとってはあまりにも急で、また天皇にとってはあまりにもタイミングがよかったので、義満は暗殺されたと主張する人は多い。
簒奪計画はすべて義満一人が推進したもので、将軍義持や管領斯波義将は一切タッチしていなかった。義持は、義嗣と違って父から愛されてはいない。理由はわからないが、それによって父への不満や憎しみがあったことは間違いない。義持は父の計画をリセットし、すべてを以前の状態に戻したのである。
どうもこの二人は、義満のやり方を苦々しく思っていたフシがあった。
政庁だった北山第は、鹿苑寺を残して破壊された。
義持が父を憎んでいただろうと思うのは、この点である。父の遺産まで破壊するということは、相当のものだったろうと想像できる。
この残された鹿苑寺が今の金閣寺であることは言うまでもない。
一方、義嗣の人生は父義満の死によって暗転する。
義嗣は、義持の命で母親共に北山第から追放されたが、それでも官位は1409年には正三位、1411年には従二位と昇進し、この年には権大納言にまでなった。しかし1416年、上杉禅秀の乱で上杉方に加担したとされて相国寺へ幽閉され、後に殺されている。
◆幕府の衰退
1428年足利義持が43歳で死ぬと、後を継いだのは僧籍にあった義教(よしのり・・義満の三男。義持・義嗣の弟)だった。5代将軍だった義量(よしかず、義持の子)は1425年、隠居した義持に先立って死んだため、義持は将軍を代行していた。
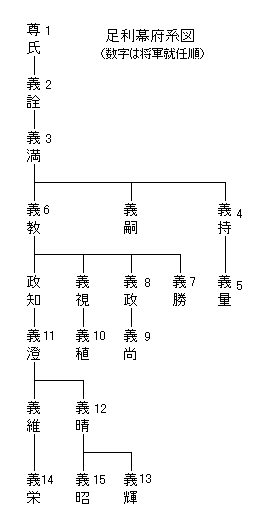 |
足利義教(1394〜1441)が将軍になったのは義持の遺言でもなければ、宿老達に推されたわけでも、お家騒動を武力で勝ち抜いたわけでもない。4人の将軍候補がいるなかでくじ引きによって選ばれたのである。
このあたりから幕府は衰退しはじめる。
義持の葬儀に参列した公家達は、朝廷へ出仕停止を命ぜられる。
天王寺別当職、伊勢神宮祭主の人事では、幕府から提出された案は拒否された。この人事権は義満が獲得したものだった。新将軍義教が提案した改元案もまた拒否された。
もっとも人事も改元も紛糾はしたものの最終的には幕府(義教)の意見が通ったが、それでも義満の時代には考えられないことだった。
しかし、そうこうしているうちに義教にとっては、朝廷どころではない事件が起きてしまった。
九州の騒乱、比叡山との対立、鎌倉公方足利持氏の反乱である。
足利幕府は初代将軍の尊氏が、彼に協力した大名達に気前よく領地を分け与えたため、大名の力が大きくなりすぎて幕府もコントロールできないようになっていた。
このような世の乱れは幕府の統治能力が弱いからだ
・・・・・義教はそう考えたに違いない。義教はこうした「敵」に対し、徹底的な弾圧と恐怖政治で報いた。
九州は関東と同様に騒乱の絶えないところで、このときも大内、少弐、大友といった有力大名が九州での覇権をめぐって争っていたのだ。ここで義教は戦死した大内盛見の甥、持世に大内家を相続させ九州探題として九州を支配下に置くことに成功した。
|
比叡山との対立は、幕府側の奉行だった飯尾為種と僧侶の光聚院猷秀の不正を、比叡山側が訴えたことにはじまる。
当初義教は、飯尾と猷秀を配流することで事件の解決を図ったが、比叡山はそれに満足せず、比叡山に同調せずに中立を決め込んでた園城寺を攻撃、焼き討ちするという事件が起きた。
激怒した義教は、直ちに比叡山を包囲したが、このときは比叡山側が降伏したので兵を引いた。
1444年、比叡山が足利持氏とともに義教を呪詛しているとの噂が流れると、義教は再び比叡山を包囲。しかし宿老たちの赦免要請に渋々和睦したのである。
しかし義教は、比叡山を許してはいなかった。
1445年、危害は加えないから上洛せよ、との言葉を信じた比叡山の代表者4人が幕府に出頭すると、義教はこれを捕らえ首をはねてしまうのである。驚いた延暦寺では抗議のため根本中堂に火をかけ、24人の僧侶が焼身自殺。
この炎は京からも見え、人々に衝撃を与えた。義教は、比叡山について噂する者は斬罪に処す、というふれを出したが、ある商人がこの禁を破ったため処刑されている。こうした義教のふるまいについて伏見宮貞成親王は、日記に「万人恐怖」と記している。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
赤松円心といえば室町幕府創業の功臣である。
その円心の玄孫に赤松満佑(1381〜1441)という男がいた。
播磨(兵庫県南部)の大名である。
ところが義教は、赤松一族の赤松貞村という男を寵愛し、貞村に播磨を与えると言ったらしい。
この噂を聞いた満佑は不安になった。
1441年、足利義教は、赤松満佑の京屋敷に招待された。
義教は何の疑いも抱かなかったのであろうか。
庭の池に住みついている小鳥が可愛いので、是非見に来てくれと言う満佑の言葉に、のこのこと満佑の屋敷に出向いた義教は宴の最中に暗殺されてしまうのだ(嘉吉の乱)。
義教に従って赤松屋敷を訪問した細川持之、畠山持永、山名持豊、一色持親等の錚々たる大名達は、あわてるだけで何もできず、満佑は悠々と屋敷を後にして播磨に戻ったのである。その後満佑は追討軍と戦い敗死した。
足利幕府の勢力は、義満の時代が絶頂期で、義教まではかろうじて保ってきたものの、その後は急激に衰えたと言える。
後を継ぐ将軍にはろくなものがおらず、幕府の権威・権力は時代とともに下がる一方であった。それはたとえば8代将軍、足利義政(1436〜1490)の、施政者としての驚くべき無責任ぶりを見ればいい。
1461年、未曾有の飢饉に襲われた京都周辺は餓死者があふれ、賀茂川は死者で堰き止められるほどだった。この時、義政は政治の責任者として何をしたか。
何もしなかったのである。
それどころか飢えに苦しむ民衆を無視して税を重くし、私邸や御所(花の御所)を改築し、絵画・陶器のコレクションに耽っていたのだ。
あまりのことに後花園天皇が一篇の詩で諌めたことは有名である。
|
残民争採首陽薇
処々閉炉鎖竹扉
詩興吟酸春二月
満城紅緑為誰肥
|
(飢えに苦しむ民衆は首陽山のわらびを採っている)
(どの家もかまどの火が消え、扉を閉ざしている)
(本来心がうきうきして詩心がおきる春二月なのに)
(花や木々は誰のために咲いているのか)
|
首陽山とは、古代中国で周の武王に諌言して怒りにふれた伯夷・叔斉(はくい・しゅくせい)の兄弟が隠れた山。兄弟は山のワラビを食べて飢えをしのいだが、やがて餓死したという。
後花園天皇は義政に、お前の悪政のせいで人民は伯夷・叔斉のように飢えている。何とかしろ、と諌めているのだが、義政は一切耳を貸さなかった。
幕府の支持率(?)低下には歯止めがきかない。
権威も権力も相対的なものだから、幕府の権威が低下するのと同時に天皇の権威は上昇した。しかし、それに追い討ち(?)をかけるようなことをすでに足利義教の代でやっていたのだ。綸旨の要請である。
◆綸旨は麻薬
綸旨(りんじ)とは天皇が発する命令書で、朝敵征伐などが主なものになる。
朝敵征伐の場合、治罰の綸旨ともいう。
ちなみに上皇の命令書は院宣といい、皇太子や親王のそれは令旨(りょうじ)という。
史上有名な令旨といえば、平家討滅を命じた以仁王(もちひとおう)の令旨だろう。源頼朝はこれを受け取り挙兵した。
足利義教が天皇に綸旨を要請したのは、足利持氏の反乱に手を焼いたからで、当初朝廷側はこれを足利氏内部の出来事として、介入はしなかった。
朝廷の判断は正しい。
幕府側から見れば幕府が軍事政権である以上、このような私的なことで綸旨を請うなど、やってはならないことだった。
自分(幕府)が解決できない紛争を、他人(天皇)の手を借りて解決を図るなど醜態この上ない。何のための軍事政権なのか。
足利義満は若いころはともかく、壮年期以降は決して綸旨を請わず、内乱があってもすべて自分の力で解決してきた。
山名氏清・満幸による明徳の乱(1391年)、大内義弘による応永の乱(1399年)などである。ある公家は、綸旨を要請しないことに不満を持ち、朝廷をないがしろにしていると、日記に書いたほどだった。
天皇に権威を持たせてはならない ・・・・義満の方針は一貫している。
綸旨は一種の麻薬なのである。
いったい室町幕府にとって綸旨とは、譬え(たとえ)は悪いが日本銀行による国債引き受けのようなもので、発給すれば、当面の効果は大きいが、同時に幕府の権威の低下(国債の場合はインフレ
―
経済混乱)につながるという、いわば阿片のような麻薬に似た存在である。
一度実現すると止められなくなる、という点でも阿片に似ている。果たせるかな、これ以降、幕府は綸旨の頻発に踏み込むことになる(室町の王権/今谷明)
実際、足利持氏追討(1438年)で復活した綸旨は、その後数十件になるという。中には治罰だけではなく寺社公領の安堵に関するもの、幕府内の人事に関するものまで発給されるようになった。
ほどなくして起きた応仁の乱(1467年)と明応の政変(1493年)をキッカケに、日本は戦国時代に突入するが、足利幕府にはもはや乱を収拾する力はない。
収拾するどころか、1473年には施政者としてその任に当たるべき将軍足利義政は引退し、将軍職を息子の義尚に譲ってしまったのである。このとき義尚は8歳の童子で、応仁の乱が終わるのはその4年後だから、まだ乱の真っ最中であった。
義政の無責任ぶりは人間ばなれしているが、誉めるべき点があるとすれば、芸術的センスであったろう。彼が愛した文化は、今日、東山文化として知られる。また日本庭園や書院造などの建築方式、能、茶道、華道など、日本文化の源流はこの時代にある。
義政は夫人の日野富子を嫌い、富子と別れて暮らすために造った隠居屋敷が、日本の名庭園。いわゆる銀閣寺である。もっとも義政自身はその完成を見ることなし1490年、55歳で病死したが。
 |
|
銀閣寺 |
無責任なのは義政だけではない。
日野富子もいい勝負である。
彼女は蓄財で有名だが、そのすさまじさは応仁の乱の最中、なんと戦費を細川・山名両氏に貸すほどであった。
この両氏は互いに敵として戦っている仲なのだ。金など一切貸さなければ、両氏とも戦費調達に行き詰まり、戦いはもっと早く終わったに違いない。
さて、治罰の綸旨の発給とは、つまり自分は正義の軍で、敵は賊軍であることを天皇に認めさせるために要請するのだが、その要請も戦国時代にはなくなっていた。代わりに出てきたのが官位の要請だった。
◆戦国大名の登場
戦国大名は、それまでの守護大名とは定義が異なる。
守護大名とは幕府から任命された、いわば地方官だが、これに対して戦国大名は守護大名が戦国大名になることもあれば、元々土着していた豪族(国人)や、その家来が成り上がってその国を支配し、戦国大名になることもある。
何が違うのか。
まず支配力の強さだろう。
守護と国人との間には主従関係はないのである。
守護大名として赴任する国には、古くから土着している国人達がいる。彼等は、支配領域は守護に比べればはるかに狭いながらも、一城の殿様としてのプライドもある。幕府の命ということで赴任してきた、見ず知らずの男(守護大名)に頭を下げるなど面白いはずがない。
守護大名の中には幕府から任命されても、その国に赴任しない大名も多かった。
赴任せず京にいるのである。なぜかといえば、常に幕府と接触していないと、いつ守護を罷免されるかわからないからだった。
足利幕府とはそういう体質があった。
在京のままでは守護としての職務が果たせないので、守護大名は現地の有力な国人を代理として置かざるを得ない。これが守護代である。現地の国人層出身の守護代と、他の国人達との結びつきの強さは、守護と国人達との関係の比ではない。
守護大名の役目とは簡単にいえば徴税と訴訟決裁で、守護大名と国人の間には主従関係はないから国人の下に位置するその家来や、農民達に守護大名の支配がおよぶはずがない。また戦争が起きても守護大名は、国人達に命令を下すことができなかった。この場合は命令ではなく、要請というカタチにならざるを得ない。
一方国人達からみれば、守護代は守護の代理というだけで、元々は自分達と同じ国人である。
当然主従関係はないし、代理と言うだけで威張られては面白くない。
このように守護にしろ守護代にしろ、その支配は相当不安定なものだった。
しかし守護大名には、領国支配の正当性はある。
なにしろ政府(幕府)から正式に任命されているし、朝廷からは信濃の国なら信濃守、陸奥の国なら陸奥守という辞令(官位)をもらっているのだ。
これに対して戦国大名とは、なんらかの方法で本来支配権のない国人達を家臣に組み込み、支配組織の再編成に成功した大名をいう。これによって彼等は国人層はもとより、その支配下にある農民などの一般層をも支配することになるのだ。
守護大名から戦国大名に転じた代表例は武田信玄であろう。
また国人層から成りあがって、守護大名を追放するか倒すかして、さらに自分と同列の他の国人達を家臣にした人もかなりいる。
これも戦国大名である。たとえば織田信長の父、信秀がそれである。
元々尾張の守護は斯波氏だったが、織田家はその家老職だった。
しかし信秀・信長の織田家は、家老職の織田家の一族とはいえ傍流で、本家の家老職だった。斯波氏からみれば家臣の、そのまた家臣である。
織田信秀は辣腕をふるい本家を凌ぎ、弱体化していた斯波氏を凌ぎ尾張の半分を支配した。尾張全体を支配するようになったのは信長の時代からである。
力だけで成り上がった戦国大名には、領国支配の(法律上の)正当性はない。
彼等はその正当性を官位に求めた。すなわち朝廷に多額の献金をし、官位(信濃守や陸奥守など)を得るのである。
ところが朝廷への献金は、実はこれはルール違反だった。
官位の要請は、幕府が窓口となって朝廷に申請するのが規則だったが、戦国期にはこの規則はまったく無視されて、戦国大名たちは直接朝廷と交渉するようになる。幕府の権威はそこまで落ちていたし、長い戦乱で直轄領が荒らされ収入が激減していた朝廷も、献金欲しさに官位を乱発したのである。
したがって戦国時代は、官位のインフレ時代でもあった。
たとえば美濃守というのは、その国には一人しかいないはずだが、複数の大名が同時に美濃守になることもあったし、官位を得ないで美濃守を自称する武将も相当数出てくるアリサマだった(信長は上総介を自称していた時期があった)。
余計なことながら、美濃守とか信濃守とか越前守とか言うが、守とはそれぞれの国における行政上の最高官を言う。現在で言えば県知事の意味だが、これは律令制上の役職である。
この古びた制度を否定し、武家の世を作ったのが源頼朝だったが、その後数百年間。江戸時代の終りに至るまで、この制度が生きていたと言うのはどういうことであろうか。
Index
ティータイム 前へ 次へ